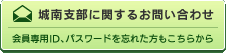経営お役立ちコラム
「マーケティング」とは、一言で表すと「売れる仕組みづくり」であり、製品開発や想定顧客の選定、流通経路の設定、販売促進の実施等、その範囲はとても広いものです。そこで今回は中小企業の方に向け、既に販売する商品・製品が決まっていて、それをどのように他社と差別化して販売するかに主眼をおいてお話しします。
1.自社の商品・製品の『価値』を整理する
お客様が本当に欲しいものは、「商品」そのものではなく、「商品を使うことによって起こるよいこと」をご理解ください。例えば口紅が欲しい人は、口紅そのものが欲しいのではなく、口紅を塗ることによって「顔色がよく見える」「美しく見える」ことを期待している、ということです。つまり商品の『価値』とは、お客様の望む「よいこと」「嬉しい」を引き出したり、「困っ…
続きを読む
「経営革新」という言葉を聞いたことはありませんか。
中小企業診断士は、経営革新の相談に乗ることもあります。
経営革新とはどのようなことを指すのか
Q&A方式で見ていきましょう。
Q:経営革新とは、具体的には何を意味するのですか。
A:経営革新とは、毎年、同じ営業・生産を繰り返すのではなく、
企業を取り囲む環境変化などに対応して経営のスタイルを変えていくことです。
つまり、(1)自社の現状や課題を見極めたい(2)自社の業績をアップさせたい
(3)自社の経営の向上を図りたい場合に、経営革新への取り組みを勧めます。
Q:具体的には、どのように進めればいいのですか。
A:まず、自社の事業の現状や課題の見極め、経営目標を明確にしましょう。
また、業界や…
続きを読む
14/12/31 21:00 | カテゴリー:
読みもの | 投稿者:
広報部 コラム 担当
1.新商品開発は簡単?
「新商品開発は、簡単!」ってなかなか聞いたことがありません。
一から新商品を作り上げていく産みの苦しみは、並大抵なことではない一方で、「好きこそものの上手なれ」なのか、思いのほか、すんなり行くこともあります。
とはいえ、すんなり出来たからと言って、それが良く売れるかは、また別問題です。今回は、”商品開発”を8つのステップで整理して進める方法をご紹介します。
2.新商品開発の8つのステップ
(1)アイデアの創出
ゼロから立ち上げていく場合には、アイデアの創出に本当に苦労します。ブレインストーミングは、最も有名で良く使われる方法です。複数人でアイデアを出し合い、紙やホワイトボードに書き出します。荒唐無稽でも否定せず、どんどん出していくことが…
続きを読む
・社長!こんなことでお困りではありませんか?
・「受身体質の社員が多い!」「言われたことしかしない!」
「気が利かない!」「前向きな提案がない!」「社内に活気がない」
「後を任せられない」「売上が停滞している!」
“社内をもっと活性化させたい”“社員の活力を引き出したい”……等々。
・人材の育成・運用問題で、苦慮していませんか?
そんな多くの社長様の悩みに応える~人材の育成及びその運用術~について、4つの留意すべき成功要因をご提示いたします。事業運営の指針として取入れ、実行されることをおすすめします。
テーマは、「自律」と「リーダーシップ」です。
1.社員が成長する“生き活き”とした組織を創る。“自律する人材”の育成が肝要です。
「モノは作れば売れる」というよう…
続きを読む
1.MOT(Management of Technology、技術経営、技術マネジメント)とは
製造業においてMOTの重要性が唱えられて久しいが、その概念や手法の曖昧さにより、いまだ広く定着するに至っておりません。
様々な学者・専門家により不統一な概念・手法が示されており、曖昧さを助長しているという指摘もありますが、1つだけ揺るぎない概念・手法があります。それは、「(1)技術の経営(マネジメント)」、「(2)技術による経営(マネジメント)」の2本柱から成り立っているという点です。
これは、前者が技術を創出していく過程での「技術プロセスマネジメント」であり、後者が創出した技術を製品化などで収益に結び付ける過程での「技術アウトプットマネジメント」です。
さらに「技術プロセスマ…
続きを読む
14/07/31 21:00 | カテゴリー:
読みもの | 投稿者:
広報部 コラム 担当
(1)経営戦略立案の重要性
中小企業の経営支援をしていく中で感じることがあります。 それは、経営者は常に内外の問題に対峙しているということ。得意先からの要請、 外注先の廃業、資金調達、納期、品質、社員の退職など、例には枚挙にいとまが ありません。ともすれば、経営者の意識は短期的・対処的になりがちです。 だからこそ、経営者は中期的な視点で戦略を考える機会を持つことが大切で、 施策として年度で経営戦略を立案することを提案しています。 中期的な戦略へ取組みを実践している企業は、金融機関にも好印象を与えることも あるからです。
(2)バランス・スコアカードによる経営戦略立案
経営戦略を立案する代表的なツールとしてバランス・スコアカード(以降BSC)が あります。BSCについての解説…
続きを読む
14/06/30 21:00 | カテゴリー:
読みもの | 投稿者:
広報部 コラム 担当
<div>
近年「クラウド」という言葉は広く認知され、一般的な用語となってきています。しかし、言葉は知っているが具体的な内容やメリットはよく分からない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか?今回は、クラウドサービスの主なメリットと中小企業のクラウドサービス利用状況についてまとめました。
まずクラウドサービスとは何か。主な要素は以下の通りです。
・ネットワークを通じてコンピュータの資源・機能が提供される
・サービスとして提供され、利用者は利用量に合わせて費用を支払う
・利用できるコンピュータの資源は増減可能である
そしてクラウドのメリットは何か。主なメリットは以下の通りです。
1.コスト削減
クラウドサービスを導入すれば、高額なシステム購入…
続きを読む
14/05/31 21:00 | カテゴリー:
読みもの | 投稿者:
広報部 コラム 担当
1.日本の医療の課題と国際化
日本の医療システムは、国民皆保険制度下、医療サービスへのフリーアクセスを維持しつつ、質の高いサービスを提供してきた。しかしながら、医療保険財政の悪化、高齢者の増加、医療サービスの高度化等のさまざまな課題に日本の医療システムは直面しており、今後も長期的に同水準のサービスを提供できるかが、不安視されている。
このような状況を打開して、医療システムの持続的成長を図る戦略として注目されているのが、成長産業としての医療システムの国際化である。日本の医療機関が、医療機器・製薬メーカー等と海外に進出し、現地の事情に即した医療サービスを開発することを通じて、現地医療の質の向上に貢献するとともに、その成果を国内医療にも還元することを期待されている。また、海外からの患者…
続きを読む
14/04/30 21:00 | カテゴリー:
読みもの | 投稿者:
広報部 コラム 担当
<div>
1.ネットショップ研究会について
当支部のネットショップ研究会は、2011年3月に発足したまだ若い3年目の研究会です。毎年何名かの新規入会者を迎え、現在は30名程度の登録を頂いています。
主な活動は、インターネット販売を支援するためのノウハウの取得や、現在進行中の支援案件の進捗共有、支援に関する参加メンバーから他の会のメンバーへの相談、ディスカッションです。当研究会は、実務も行うことができる研究会であることが特色です。実際にメンバーの持ち込んだ案件について、参加者を募り支援活動を行っています。今回はその活動内容について紹介します。
2.基本的な支援の方向性
インターネット販売においては「売上=アクセス数×転換率×平均単価」という公式が基本原則です。ど…
続きを読む
14/03/31 21:00 | カテゴリー:
読みもの | 投稿者:
広報部 コラム 担当
銀行及びサービサーにて企業再生業務に携わってきた経験より、
小規模企業の企業再生についてまとめました。
さて、一般的に言われる企業再生手法としては私的整理、法的
整理含め、会社分割やM&A、DES/DDS等の金融・法的手法による
BS面のアプローチが主流となっております。しかし、小規模企業
の再生実務を考えた場合、これらの手法を適用するには少々無理が
あるでしょう。そもそもこれらの外科的手法は、中堅中小企業、
金融機関でも大口の融資先を対象としており小規模企業向けの手法
ではないのです。
それでは、小規模企業の再生はどう行うべきか。基本的には
今ある限られた経営資源の中でPLを改善していくことになりますが、
単なる売上改善策では再生は実現しないと考えます。再生企…
続きを読む
14/02/28 05:59 | カテゴリー:
中小企業経営 | 投稿者:
椎木忠行