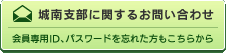経営お役立ちコラム
事業を行う上で大切な目標の一つは利益を出すことである。
では会社を存続・発展させるために必要な“適正利益”を残すために
何をすればいいのだろうか?ズバリ、その答えは3つしかない。
1.売上拡大を実現する
2.限界利益率を改善する
3.固定費を削減する
この3要素を噛み砕いたものが“SPEC-A”である。
ここでそれぞれの意味を解説したい。
Sales:「売上」をいかに拡大するか
Profit:「利益」をいかに獲得するか
Expense:「経費」をいかにコントロールするか
Cost:「原価」をいかに管理するか
Activate organization:「組織活性化」をいかにして行うか
利益拡大を実現するためには、これらをコントロール、または変革
し…
続きを読む
14/02/01 10:30 | カテゴリー:
中小企業経営 | 投稿者:
椎木忠行
とても残念なことですが、お客様というのは、私達、つまり販売側-小売、卸、
メーカー、サービス含め全ての事業体-のことを忘れてしまうものです。
自分に置き換えて考えてみましょう。
一ヶ月前に外食したお店の店名を覚えていらっしゃいますか?
一年前に購入した手帳のメーカー名を覚えていらっしゃいますか?
それはどのお店でお買いになりましたか?
大体の場合、よほどインパクトのある出来事があったり、感動するようなサービ
スがあったりしなければ、忘れているものですね。
しかし、私達、事業体である企業は、相手は自分のことを覚えていてくれている
と誤解しているのではないでしょうか。
先日、ある焼きたてパンを売るお店にうかがいました。店長さんは、販売促進
そのものに嫌悪…
続きを読む
13/12/31 23:42 | カテゴリー:
マーケティング | 投稿者:
椎木忠行
1.ワークショップとは?
近年、ワークショップは新しい学びのスタイルとして学校の授業
や企業研修などに取り入れられています。講義など一方的に知識を
伝達するのではなく、参加者同士が語り合い、また共同で何かを創る
活動を通して、気づきや学びを得るのがワークショップです。
社会には様々な情報が溢れ、人々が持つ価値観は多様化しています。
このような中でも社会が発展し続けるためには、人々がお互いの
価値観を認め、理解し合うことが必要になります。ワークショップは
このような相互の認知と理解を促進する場でもあるのです。
社会の縮図である企業でも同じような問題が起こっています。
顧客ニーズを把握することの難しさや組織における世代間の
コミュニケーションギャップなど、情報の氾濫…
続きを読む
13/12/01 07:15 | カテゴリー:
人事、人材活用 | 投稿者:
椎木忠行
(1)はじめに
今回は、製造業の生産管理の中でもスケジューリングと情報システム
の活用についてまとめました。理想は、生産の進捗と情報システムとが
リアルタイムに連携し、納期の短い注文が割り込みで入ったり、
トラブルで生産が遅れたりした時に、原材料や人員といった資源の
再配分計算、再スケジューリングなどを短時間に行い、それに基づいた
生産指示が即座に生産に反映されることだと思います。
皆さんの生産工程では、どのようにスケジューリングを行っている
でしょうか。
(2)スケジューリングの難しさ
製造対象のリードタイムにもよりますが、完全受注生産に近いほど
短期間のスケジューリングしかできない場合が多く、このような場合は
納期優先になりがちです。注文が少ない場合で…
続きを読む
1.BCPとは?
「BCP(事業継続計画)」の策定とは、災害などの緊急時に行うべき行動や、
緊急時に備えて平常時に行うべき行動をあらかじめ整理し取り決めておくことです。
単なる災害対策ではなく、被災後に事業をどう継続させるかについての計画です。
たとえば、緊急事態に遭遇した時に、社長は適切な対応がとれるかもしれません。
しかし、社長が指示をだせない状況になったときに企業として対応がとれる
でしょうか? BCPは、企業のボトルネックを解消しようとする取り組みでもあり、
通常期の経営で考えるべき項目のひとつです。
ただ、起こるかどうかはっきりしないものに対しての計画となるため、
まずは身の丈にあった実現可能なBCPを策定し、それを積み重ねて行くと
よいでしょう。資金を必要とす…
続きを読む
13/09/30 21:28 | カテゴリー:
中小企業経営 | 投稿者:
椎木忠行
(1)知的資産経営報告書とは何か
最近、「知的資産経営報告書」なるものを眼にすることが増えて
います。しかし、そもそも、“知的資産”とは何なのでしょうか。
経済産業省等のホームページによれば、知的資産とは知的財産(権)
を含む広い概念であるとし、具体的には、知的財産(権)に加えて、
例えば、人的資産、組織力、経営理念、顧客とのネットワーク、
技能等を含むとしています。そして「知的資産経営報告書」作成の
効果のひとつとして、金融機関との良好な関係維持をあげています。
とするならば、多くの小規模企業にとっての課題であるポスト
金融円滑法対策ツールとして使えないものでしょうか。
そこで、「知的資産経営報告書」の活用について、述べてみます。
(2)知的資産経営報告書活用…
続きを読む
13/08/31 08:30 | カテゴリー:
中小企業経営 | 投稿者:
椎木忠行
(1)はじめに
中小企業等の、電力会社との契約が高圧小口電力需要家に対して、
電力需要抑制の取り組みを促進するために、エネルギー管理
システム(BEMS)導入促進事業費補助金が、平成25年度末
までの予定で実施されています。中小企業事業者にとって、福島
の原発事故以来の節電への協力はもちろんのこと、電気料金の
値上げ等により、経営面からもエネルギーコストの削減は重要度が
増しています。補助金を活用した電力量の削減にむけて、補助金
制度の概要をご紹介します。
(2)制度の背景
電力需要の視点から、中小ビル等の高圧小口需要家(契約電力
50kW以上500kW未満)は日本全国で約77万口あり、
全国の電力使用量の2割を占めています。また昼間に限れば、
使用電力…
続きを読む
地域需要創造型等起業・創業促進事業に関する補助金制度に
ついてご紹介します。
地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業、既に事業を
営んでいる中小企業・小規模事業者において後継者が先代から
事業を引き継いだ場合などに業態転換や新事業・新分野に進出する
第二創業、また、海外市場の獲得を念頭に事業を興す起業・創業を
支援することにより、地域における需要創出並びに中小企業・
小規模事業者の活力の向上を促すことで、経済の活性化を図る
ことを目的として、これらの起業・創業、第二創業を行う者に対して、
その創業事業費等に要する経費の一部を補助する事業が、
「平成24年度地域需要創造型起業・創業促進事業」です。
本年3月から現在まで二回の募集が行われており、第一回募集
…
続きを読む
今回は、コーチングの要素として3番目に重要な「認める力」に
ついて解説します。
【認める力とは】
コーチングでは、「人間の可能性は無限」という前提条件を置いて
います。その可能性をうまく引き出してやるのがコーチングです。
その中で、「認める力」は、「聴く力」「問う力」に続き、3番目に
重要なものです。「認める」という言葉の語源は、「見(る)」と
「とめる」です。つまり、「認める」というのは、「相手のことを見て、
心にとめる」ということなのです。
上司が部下を動かそうとする時には、通常は「命令する」という
形を採ると思います。確かに、上司には組織から与えられた権限が
ありますから、上司の命令は聞かなくてはなりません。しかし、
「命令」だけですと、部下は理屈で…
続きを読む
13/03/10 10:01 | カテゴリー:
人事、人材活用 | 投稿者:
椎木忠行
前回はコーチングの基本的要素について解説しました。
基本的要素とは「信じること」「認めること」「任せること」です。
これらを実現するための具体的スキルは三つあり、それぞれ
「聴く力」「問う力」そして「認める力」に分類することが出来ます。
今回は「聴く力」と「問う力」について解説していきます。
【聴く力とは】
経営者にとってコミュニケーションは重要なスキルです。では、
「コミュニケーション」とは一体何でしょう?コミュニケーション
とは本来双方向のやり取りであり、自分の事を話すだけではなく、
相手の言う事にも耳を傾けて双方向で言葉を交わすことで、相互理解
を深めることが必要です。それを実現するためのスキルが「聴く力」
なのです。
■ 「聞く」と「聴く」の違い
…
続きを読む
13/02/23 11:54 | カテゴリー:
人事、人材活用 | 投稿者:
椎木忠行