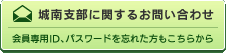経営お役立ちコラム
1.はじめに
前回に続き、下町に3代続く石材店「寺内石材店(石貫)」の家族、「寺内貫太郎一家」(初回放送1974年TBSテレビ)を想定モデルとして事業承継を考えていきます。家族は、主人公兼会社経営者、実母、妻、長女、長男(後継者と想定)です。前回で事業承継については、4代目となる長男に、企業の知的資産を引き継ぎつつ、将来展望の経営デザインを親子で描くことになり目途がつきました。そして、今回は個人資産の承継として相続準備を進めます。
2.遺書と遺言
相続準備として遺言を作成している割合が少ないのが実状であり、まだまだ活用されていません。家族の仲良いから相続は問題ないということや、自分が亡くなったあとは話し合えばいいということをよく聞きます。確かに問題のない場合も多いですが、親族内…
続きを読む
19/09/30 21:00 | カテゴリー:
中小企業経営 | 投稿者:
広報部 コラム 担当
1.はじめに
下町に3代続く石材店「寺内石材店(石貫)」。頑固な親父である会社経営者は気に入らないことがあるとすぐにちゃぶ台をひっくり返すようなワンマンですが、気が優しくどこか憎めないところがあります。ピンときた方もいらっしゃると思いますが、昭和の有名なドラマ「寺内貫太郎一家」(初回放送1974年TBSテレビ)の設定です。都内の中小企業を描いたホームドラマであり、家族や老い、街のつながりなどが描かれています。
これから、2回に渡り、「寺内石材店」を想定モデルケースとして、事業承継における知的資産経営の活用、遺言の活用について、令和の時代に置き換えて考察します。
石材店の人物関係(かっこ内は出演者名)は、主人公兼会社経営者(小林亜星さん)、実母(樹木希林さん)、妻(加藤治子さん)、…
続きを読む
19/08/31 21:00 | カテゴリー:
中小企業経営 | 投稿者:
広報部 コラム 担当
<前編のおさらい>
ジオラマ(立体模型)を全て手作りで制作しているD社は、マンパワー不足に陥っていました。その品質は伝統工芸品の域までに達していましたたが、制作に時間を要するため営業活動に時間がさけず、お客様に品質を理解してもらえないことも増えてきました。その結果、価格競争に巻き込まれ失注も増えてきました。
中小企業診断士(以下、診断士)として、D社の高い品質という強みを生かすため、都道府県から工芸品として表彰を受け、客観的評価を得て差別化をすること、それをHPやマスコミを使って広告宣伝を行い営業活動とすることを提案しましたが、D社のM社長からの反発は予想以上に強いものでした。
5.M社長への懸念への説明
・商工会議所や振興公社などは中小企業を助けるものです。最初は敷居が高く…
続きを読む
19/07/31 21:00 | カテゴリー:
中小企業経営 | 投稿者:
広報部 コラム 担当
1.はじめに
小規模事業者は経営資源、特にマンパワーの制限から折角良いアイデアでも諦めざるを得ないものが多いと感じています。我々診断士の支援の多くが、経営革新計画や経営力向上計画などの経営計画立案や補助金(助成金)申請などに留まっていないだろうか、マンパワーの不足に対しもっと直接的に支援できないだろうかと前々から私は考えていました。
現在支援中のD社は営業拡販の一環として表彰制度を使い差別化し宣伝することで売上・利益率向上を目指しています。小規模事業者からの視点を含めた表彰制度の活用と診断士としてのその支援内容につき2回に分けて紹介致します。
2.D社の状況
D社はジオラマ(立体模型)の制作を行っている個人事業主です。今年で開業10年になります。社長一人であり他に従業員はい…
続きを読む
19/06/30 21:00 | カテゴリー:
中小企業経営 | 投稿者:
広報部 コラム 担当
フェイスブック(FB)、ツイッター(TW)、インスタグラム(IG)、LINEなどのソーシャルネットワーキングサービス(SNS)が普及し、多くの企業がSNSで商品やサービスをPRするようになりました。今回のコラムでは、SNSを活用していかに自社の「ファン作り」と商品・サービスの「販売促進」を行い、売上増につなげるかを取り上げます。
(1)「ファン作り」の事例と方法
革製品メーカーの土屋鞄製造所(東京都足立区)は、自社製品の魅力や品質へのこだわりをFBやIGを通じて巧みに発信し、ファン作りに成果を挙げていることで知られています。職人手作りのバッグなどを販売する同社のFBを約30万人がフォローしており(2019年5月現在)、その投稿写真の美しさには定評があります。またセールやキャン…
続きを読む
はじめに
社員は社長の言動や行動を見ています。社長もやっているのだから、自分も少しぐらいやってもいいじゃないか、と社員が考え始めることは会社経営にとって、大きなリスクとなります。前回は社長の「お金に関連した公私混同」を題材に、社長ご自身のミニマムコンプライアンスの大切さをお話しました。今回は、社員にも横領など不正行為をさせない、社長としての社員管理術についてお話しします。
(1)社員管理のポイント
経理はベテラン一人にずっと任せている、事務所の机にはいつも現金が入った金庫がある、営業マンの出張費・交通費は数ヶ月後にいつもまとめて精算している、このような事例に思い当たることがありませんか?社員管理のポイントは2つあります。一点目は、社員に不正行為をさせないルールや仕組みづくりです…
続きを読む
19/04/30 21:00 | カテゴリー:
中小企業経営 | 投稿者:
広報部 コラム 担当
はじめに
昨年10月の本コラムで、同じ題名で、コンプライアンス違反や不祥事に対する社会の目、ミニマムコンプライアンスを実践することのメリット、および社内展開時のポイントなどを総論的にご紹介しました。今回と次回4月号では、「お金」という
最も身近な題材を取上げ、ミニマムコンプライアンスの深堀を試みます。
今回は、社長の生活感にマッチした具体的事例を、中国の故事になぞらえながら、社長の「心構え」や「行動」について考えてみます。
(1)「繭(まゆ)を作りて、自らを縛る」
カイコの幼虫がさなぎになるため、自分の体の周りに糸をだして繭を作る様を、自らを縛ると捉え、転じて「自分の言動や行動で自らを苦境に陥れる。
人は痛い目に合わないと気づかない」という教訓として広く知られるようにな…
続きを読む
19/03/31 21:00 | カテゴリー:
中小企業経営 | 投稿者:
広報部 コラム 担当
1.はじめに
先月の前編では、「想像する力」、「変換する力」について、ご説明しました。
今月の後編では、「まとめる力」、「見通す力」について、ご説明します。
2.まとめる力
仕訳を財務計画に「まとめる力」とは、仕訳に変換された取引を損益計算書(PL)および貸借対照表(BS)の形に集約することです。
まとめる力が必要な理由は二つありあす。
一つ目は、集約することで全体を俯瞰して考えられるようになります。
俯瞰することで、売上を伸ばすのか、原価を減らすのか、販管費を減らすのかという、新しい事業の計画を見直すポイントを見定めることができるようになります。
二つ目は、集約することで人に説明するのが簡単になります。
A社には100円で仕入れたキャベツを1個200円で、B社…
続きを読む
19/02/28 21:00 | カテゴリー:
中小企業経営 | 投稿者:
広報部 コラム 担当
1.はじめに
新しい事業を始める場合、多くのケースで「事業計画書」を作成します。
「事業計画書」を作成するにあたり、事業戦略、市場規模(マーケット)、顧客像(ペルソナ)、ビジネスモデル(どんな価値を提供してどこから対価を得るのか)、売上・利益予測(予測PL)など多くのことを整理する必要があります。
ここで特に頭を悩ませるのが売上や利益などの会計面かと思います。
なぜならば、既存の事業とは異なり売上・利益を把握する仕組みが無かったり、経験から何となく分かる“勘”が利かなかったりするためです。そこで新しい事業を始める時に必要となる会計の知識をご紹介します。
この知識とは、「想像する力」、「変換する力」、「まとめる力」、「見通す力」の4つです。
イメージしやすいようにキャベツを例…
続きを読む
19/01/31 21:00 | カテゴリー:
資金繰り、金融 | 投稿者:
広報部 コラム 担当
事業を行う上では、「契約・取引に関するトラブル」、「債権回収・債権保全」、「倒産回避に向けた事業再建」、「損害賠償対応」、「雇用・労務」、「クレーム対策」等、様々な法律問題(以下 紛争)が事業者に起こり得ます。その場合、事業者は民事訴訟か民事調停を選択することになります。
訴訟は、裁判所が紛争の原因となった当事者が主張する法律上の権利義務を基礎付ける具体的事実を証拠に基づいて認定し、法規を適用して、紛争の処理を行います。従って、訴訟手続きが複雑で、かつ、審理に慎重を期するため、相当の日時と費用とを必要とする傾向があります。民事調停制度は、訴訟の長所を活かし短所を補う目的で設けられた制度です。私は、民事調停委員を8年経験した感想から、事業者の皆様にこの制度の有用性を知っていただきたい…
続きを読む
18/12/31 21:00 | カテゴリー:
経営の法務 | 投稿者:
広報部 コラム 担当