一般社団法人 東京都中小企業診断士協会 城南支部
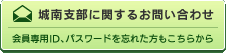
前回は、内外の食料需給状況を概観しつつ、食料価格高騰時代の到来について解説しました。今回は、このような時代をふまえた食品産業における中小企業の基本的な対策について解説します。
◆コストアップや価格転嫁の遅れによる利益率低下の対策
国内食料価格は当面上昇基調と推測され、継続的な対応の仕組み作りが重要となります。
【対策】仕入商品や原材料の見直し
仕入商品や原材料の見直しが対策となります。割安品、歩留率や汎用性が高い原材料を探索して置き換えます。探索方法は、既存仕入先での情報収集のほか、展示会やマッチングサイトの活用、地元の生産者や加工業者との直接交渉により、新たな仕入先開拓をする方法もあります。
また、商品別の収支データをもとにコストダウン効果の高いものを特定し、それらを優先して定期的に見直していくことが重要となります。
◎具体例:食品小売店が既存仕入先から、既存商品と同等品質でより低価格の海外商品も仕入れることにした(期待効果:割安品の仕入による拡販・利益率向上)
【対策】価格転嫁(企業間取引)
コストアップ分を販売価格に反映する価格転嫁が対策となります。手順は、事前準備、価格交渉という流れとなります。事前準備では該当商品の収支データ、目標取引価格、値上げ理由、顧客にとっての付加価値、市況価格、法的根拠・政府指針の確認が重要となります。
また、中小企業庁の調査(2025年3月)では、企業間取引での価格転嫁率は52.4%という結果になっており(*1)、価格転嫁が遅れがちであることが分ります。そのため、十分な事前準備や定期的に交渉をすることで価格転嫁を円滑に進めていくことが重要です。
◎具体例:食品メーカーが原材料費・人件費・水道光熱費増加分について、競合の出方などを見計らって、発注企業に対して価格転嫁の申し入れを行う(期待効果:赤字販売の回避)
◎参考情報
▶ 中小企業庁:価格交渉・転嫁の支援ツール
支援ツール「儲かる経営 キヅク君」は商品・取引先別の収支シミュレーションが可能
▶ 農林水産省:食品製造業・小売業の適正取引推進ガイドライン
▶ 農林水産省:食料システム法
◆値上げによる客離れの対策(企業対消費者間取引)
内閣府による世論調査(2024年9月)からは、食料価格高騰に対して、消費者が価格の安いものに切り替える、外食の機会を減らす、購入量を減らすなどの行動変化を起こしていることが分ります。そのため、単に同じ商品をそのまま値上げ、あるいは容量を減らし価格を据え置きする実質的値上げは、消費者の商品に対する印象を悪化させ、客離れにつながる可能性があります。
【対策】商品リニューアル・低価格商品へのシフトなど
商品リニューアルが対策となります。変更を検討する点は、価格・容量のほか、名称、ロゴ、包装、原材料、盛り付け、加工・調理方法などとなります。このときデザイン性や風味の向上など付加価値を高めると効果的です。リニューアル困難な場合は、低価格商品へのシフトや商品の小分け販売などが対策となります。これら対策は企業間取引においても応用可能です。
その他の対策としては、賞味期限が近い食品による廉価販売、国内消費者と比べ価格に敏感でない傾向があるインバウンド向け販売へのシフトなど業態の変更、支払方法や商品ポイントのような販売条件や特典施策での付加価値向上があげられます。
◎具体例:飲食店が値上げ時に、名称変更と食感・風味改善も行い商品をリニューアルする
(期待効果:値上げによるイメージ悪化回避、コストアップを伴わない変更による品質向上)
◆運転資金増大と資金調達コストの増大の対策
食料価格高騰は運転資金増大に直結します。運転資金を借入に頼っている場合は、借入増大により支払利息増加につながりがちです。
【対策】棚卸資産削減
運転資金の中でも棚卸資産は自社でコントロールが比較的容易な要素です。また、資金繰り緩和だけではなく支払利息や在庫ロスの削減につなげることも可能となるため、棚卸資産の削減が対策の基本となります。棚卸資産削減の手順は、現状把握、適正在庫の設定、削減方法検討、実施となります。削減方法には、発注や生産業務のDX化による在庫適正化があります。例えば、AI活用による需要予測システムを導入することで、販売実績や天候要因などをもとに無駄の少ない発注が可能となります。
◎具体例:パン屋が需要予測システム活用による仕入れ・生産調整により、原材料・売れ残りの商品在庫を大幅削減する(期待効果:運転資金抑制、在庫ロス低減、鮮度向上)
◆調達の不安定化による機会損失発生と品質低下の対策
食料価格高騰はモノが不足していることも意味します。そもそも売り物がなければ事業は成立しません。そのため、調達力の高さが今後の市場競争力向上の鍵を握るといえます。
【対策】調達先の多様化によるリスク分散
調達先の多様化による調達リスクの分散が対策となります。例えば、国産/輸入、卸売市場/地元生産者、二社購買による多様化です。これにより、数量・品質だけではなく価格・為替変動、流通上のリスク低減も可能となります。
なお、今後は気候変動リスク対策を考慮した調達の重要性が増してくると考えられます。気候変動への適応策に積極的に取り組んでいる生産者や冷涼な生産地からの調達、高温耐性品種の採用も検討されるとよいでしょう。
◎具体例:青果店が主力商品の産地を遠方だけではなく、地元からも仕入れるようにする
(期待効果:不作リスク低減、輸送コスト低減、鮮度向上)
◆おわりに
食品産業は、自然環境の影響を受けやすく、保存期間が短い商品・原材料が多いという特徴を持つ産業です。本稿では、それらの影響も考慮して食料価格高騰対策に効果的に取り組めるように工夫しました。皆様の経営改善に少しでもお役に立てば幸いです。
*出典
(1) 経済産業省(2025/6/20公表)「価格交渉促進月間(2025年3月)フォローアップ調査の結果を公表します」
(2) 内閣府(2024/2/21公表)「食料・農業・農村の役割に関する世論調査(令和5年9月調査)」
前回:食料価格高騰時代をチャンスに変える、中小企業のための対策ガイド(その1)
<執筆者>
清水克博
東京都中小企業診断士協会 城南支部所属。経営管理修士(専門職)、野菜ソムリエプロ、家庭菜園家。化学メーカーにて物流、購買、経理(J-SOX構築)を担当。退社後、社会人大学院生、個人事業主などを経て、現在、外資系企業に勤務。ライフワークとして食料安全保障・地震防災について研究している。