一般社団法人 東京都中小企業診断士協会 城南支部
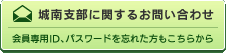
◆はじめに
近年、食料価格高騰が食品産業において大きな問題となっており、その対策が喫緊の課題となっています。本コラムは二部構成で、今回は内外の食料需給状況を概観し、食料価格高騰の中小企業への影響について解説します。次回は食料価格高騰に対する中小企業での具体的な対策などについて取り上げる予定です。
◆食に関する世界の状況
◎世界の食料需要増加
世界の食料需要増加の根源的要因は、世界人口増加と経済成長と考えられます。世界人口は2022年に 80億人を突破し、2084年には約103億人とピークになると国連により予測されています(*1)。また、人口増加に伴い世界の経済成長率(実質GDP)も伸びていくことが推測されることから、世界の食料需要は当面増加していくものと考えられます。
◎世界の食料需給と今後の見通し
今後の世界の食料需給見通しについては、農林水産政策研究所が予測しています。世界の穀物生産量は、基準年である2019-21年平均値の2,713百万トンに対し、目標年の2032年には15.2%増加して3,126百万トンとなります(*2)。また、実質価格については、基準年に対して目標年には穀物はやや低下傾向、穀物以外の主要品目は上昇傾向となります(図表1)。
図表1 主要品目別に見た基準年の価格と目標年の価格(*3)
◎世界の食料価格
2019年末からの新型コロナウイルス流行や2022年2月のロシアのウクライナ侵攻により物流・生産が混乱し、その後、小麦などの穀物価格が高騰しました(図表2)。2024年にはほぼ落ち着きを取り戻してはいますが、牛肉やコーヒー豆など価格が高騰している品目もあります。また、中東情勢の悪化や予測以上に気候変動が進行する可能性もあり、今後の食料需給は楽観視できない状況です。
図表2 穀物等の国際価格の動向(*4)
◆食に関する日本の状況
◎食料自給率の低さ
日本のカロリーベースの総合食料自給率は、2010年以降は40%を割り込んだまま37-39%と停滞しています。また、食料だけではなく、化学肥料の原料、食品産業で必要となるエネルギーも自給率が低く、日本の食料需給は国際的な影響を受けやすい状況といえます。
◎日本の食料価格
日本では、国際相場の下落を受けて輸入穀物価格は下落傾向ですが、食料の消費者物価指数の上昇は続いています(図表3)。要因は多岐に渡り、歴史的な円安、価格転嫁の遅れ、米価格高騰、穀物以外の輸入食料の一部価格高騰に加え、エネルギーの輸入依存率上昇、人口減少による市場縮小や人手不足、農業生産体制の脆弱化、気候変動という構造的要因の拡大も背景にあります。このような構造的変化は、食料価格が高い時代が到来した可能性を示唆しているともいえます。
図表3 生鮮食品を除く食料指数の動き(*5)
◆食料価格高騰の中小企業への影響
食料価格高騰は、食品産業の中小企業全般に影響を及ぼしています。主な影響として、①コストアップや価格転嫁の遅れによる利益率低下、②値上げによる販売数量の落ち込み、③運転資金増大と資金調達コストの増大、④調達(数量・品質)の不安定化による機会損失発生と品質低下があげられます。
(次回へつづく)
*出典
(1) 国際連合経済社会局人口部(2025/7/6参照)「World Population Prospects 2024」
(2) 農林水産政策研究所(2023)「世界の食料需給の動向と中長期的な見通し ―世界食料需給モデルによる2032年の世界食料需給の見通し―」, p.32
(3) 農林水産政策研究所(2023)「令和4年度 2032年における世界の食料需給見通し ―世界食料需給モデルによる予測結果―」, 第13表
(4) 農林水産省(2025/7/7更新)「穀物等の国際価格の動向」
(5) 総務省(2025/6/27公表)「2020年基準消費者物価指数 東京都区部2025年(令和7年)6月分(中旬速報値)」, 図6
第2回:食料価格高騰時代をチャンスに変える、中小企業のための対策ガイド(その2)
<執筆者>
清水克博
東京都中小企業診断士協会 城南支部所属。経営管理修士(専門職)、野菜ソムリエプロ、家庭菜園家。化学メーカーにて物流、購買、経理(J-SOX構築)を担当。退社後、社会人大学院生、個人事業主などを経て、現在、外資系企業に勤務。ライフワークとして食料安全保障・地震防災について研究している。