一般社団法人 東京都中小企業診断士協会 城南支部
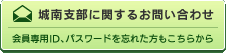
東日本大震災の被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを
申し上げますとともに、犠牲となられた方々のご冥福を
お祈り致します。
また、一刻も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
1.東日本大震災で注目されたテレワーク
3月11日、東日本大震災の発生直後、首都圏では全ての公共
交通機関がストップする事態となりました。また、余震も続いたため
多くの会社では早期帰宅指示が出たものの、歩道は帰宅者で溢れ、
また車道も車で埋まって長時間動かない、という状況が深夜まで
続きました。徒歩で帰宅できても長時間かかった人が多く、会社で
一泊した人もコンビニなどの小売店から食料や水が売り切れと
なったことで、あらためて災害対策の必要性を感じたのではない
でしょうか。
さらに、土日を挟んで翌週月曜日には、JRの運行開始そのものが
遅かったことや、その後の計画停電により電力供給が制限され、
出勤困難者が続出、自宅場所によっては長期間にわたり出勤でき
なかった人も出ました。計画停電では、東京都23区内や一部重要
施設のある地域を除き、2~4時間の停電実施により、その地域の
行政、企業は活動を停止せざるを得ない状況に置かれることと
なりまし た。事業内容によっては結果として1日単位で操業できない
ところも出てきて、特に中小企業には大きな痛手となりました。
こうした中で、震災直後からにわかにテレワークに注目する企業が
多くなりました。これは、通勤困難に対処し、自宅でも業務が行える
のではないか、という点に着目した企業が多かったのですが、
最近では、節電対策としてもテレワークに注目する企業が多く
なってきています。こうしたニーズに対応し、IT企業を中心に、
被災地向けテレワーク機器の暫定無償提供を始めとし、事業継続
計画に テレワークを組み入れた立案を提案している企業・コンサル
会社も急増しています。
そこで3回にわたりテレワークとは何か、その導入にあたっての
ポイントを解説します。
2.テレワークとは
テレワークという言葉自体、歴史が浅く一般には馴染みがない
かもしれません。社団法人日本テレワーク協会の定義を紹介すると、
「テレワークとは情報通信技術(IT)を活用した場所や時間にとら
われない柔軟な働き方」となります。つまり、場所にとらわれない
とは、自宅やサテライトオフィス、さらには外出先など事業所以外
で働くことを言います。多くの場合は、自宅において勤務する在宅
勤務が思い 浮かびますが、それ意外に、営業職の直行直帰に
代表されるように、途中外出先でパソコンを用いて業務報告や
提案書作成するような、いわゆるモバイルワークも入ります。
特に、中小企業の経営者の中には各地を飛び回り、外出先から
メールの発受信やグループウェアを使った情報共有、指示、報告
受けをしている場合が多いようです。また、時間にとらわれないとは、
たとえば9時から5時といった決まった勤務時間に業務を行う形態
だけではなく、育児・介護などで決まった時間に働けない人でも、
個人のライフスタイルに応じて柔軟に働くことを言います。勤務
時 間が固定化していても、首都圏では通勤時間から解放される
だけでもかなりの時間的余裕が出るでしょう。このことから、
ワーク・ライフ・バランスの導入に際しテレワークを前提とする企業も
出てきています。
なお、テレワークの考え方を広く取った場合、企業内における
役員・社員(非正規社員を含む)の働き方だけを指すわけでは
ありません。個人事業主やSOHO企業とのICTを活用した協業も
含めて考えることもできます。このように柔軟な働き方に加え、
柔軟な事業構造とすることも視野に入れることで、災害や停電などの
事態に対応した事業継続についての知恵出しの契機を作ることが
できます。
次回は、テレワーク導入のメリットについて記述します。
通堂重則