一般社団法人 東京都中小企業診断士協会 城南支部
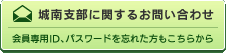
国内食品産業は76.3兆円の巨大市場であるが、中小零細企業の割合は約98%と多く事業者数は90万を超える。日本の食を支える農業、食品製造業、卸売業、小売業のそれぞれのサプライチェーン別に課題や特徴を見ながら、事業的な魅力を見ていく。
◯共通する課題
人材不足と食の安全確保であり、特に人材不足は現在の事業の成長のみならず先にあげたように中小零細比率が高いこともあり事業承継が課題としてあがっている。食の安全確保については、2009年消費者庁の創設や消費者の関心の高まり、東京オリンピック・パラリンピックを契機としたHACCPの制度化(実質の義務化)は、2018年6月に改正食品衛生法が成立し2020年6月に施行され対応について課題となっている。厚生労働省、農水省を中心に無料セミナーが全国各地で開催されているので、参加されることをおすすめしている。
◯サプライチェーンとは
物の生産から販売までの供給別の価値連鎖のことであり、その段階別に付加価値を見ていくことで、業界の構造を明らかにすることができる。川上から川下までサプライチェーン別の付加価値は、一般的には最も川下および川上の付加価値が高く、中間流通業者の付加価値は低い傾向にありグラフにしたときの形からスマイルカーブと言われている。
【農林水産物・食品の流通・加工の市場規模】
国内農業生産9.2兆円・輸入1.3兆円 ⇒食品製造業者33.4兆円
⇒市場・食品卸 ⇒小売51.2兆円・外食25.1兆円 ⇒国内消費76.3兆円
強みを活かして垂直統合をすることで企業グループのバリューチェーン構築を進めている。例えば、農業者が食品製造業に進出し、小売業者が加工業者や農業に進出している。垂直統合と言っても自社の既存の資産を活かして内製化できないか?と検討するところから始まるので、前工程や後工程の産業への進出を検討し、企業価値を高めたい。
◯農業
食品業界では、サプライチェーンのもっとも川上にあたる。農業経営体は約137万件(2015年)あり販売農家が96.5%を占めている。件数自体は10年で約31%減少しているが耕作面積地は約4%減少に留まっている。1件あたりの規模が拡大し、農業改革の方針もあり法人経営が増えている。農機のIOT化も進んでおり、さらに大規模化は進んでいく。
農業生産と一言で言っても分野は多岐に渡り、分野別にバリューチェーンも大きく異なる。大きくは、畜産と耕種に分けられる。畜産は、畜種「牛肉・豚肉・鶏肉・卵」でも大きく異なり、国産・輸入の区分でも必要な資産や経営方針は異なる、耕種では、穀物、野菜、花卉(かき)に大きく分けられ、穀類では稲作、麦、雑穀に分別され、園芸でも葉物、果菜類や、施設園芸か路地栽培でも分かれる。こうして見ると一言で農業と言ってもそれぞれは、全く異なるものとなっていることが理解いただけるだろうか。例えば、稲作で必要とする肥料・農薬・農機具でイチゴは作ることはできないのは容易に想像ができる。事業化を検討するにあたり「農業って〇〇だよね」って決めつけて話を進めることは極めて危険である。
◯食品製造業
食品製造業は地方ではその割合も大きく北海道、鹿児島、沖縄では製造品出荷額3割、製造業従事者の5割を占め地域経済を支える産業となっている。
◯市場・卸売
市場経由率は、青果60%。水産物54%、食肉10%となっており、Eコマースの拡大により取扱い金額も大きく減少している。食品卸売業の市場は、産地直送や中抜きの増加により縮小傾向であったが、近年はやや拡大傾向にある。倉庫や物流機能にとどまらず、情報やコンサルティング能力の強さを求められる。
◯小売・外食
誰もが食べ物を口にして生きていることから、身近な産業で総規模から始めることも可能なことから参入障壁は低く、女性の社会進出や1~2人世帯の増加から、加工食品市場は拡大をしている。飲食業関係は、開業率(9.7%)が廃業率(6.4%)と他の産業と比べても大きく上回っている。
ここまで食品産業のサプライチェーンを見てきたが、産業としての魅力や機会を少しでも感じていただき創業や新規分野として検討いただければ幸いである。
三海 泰良