一般社団法人 東京都中小企業診断士協会 城南支部
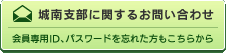
中小企業のオーナー経営者の後継者は、一般に自社株式や事業用
資産の法定相続人である子息・子女である。
オーナー経営者に複数の子供がいる場合は、子供のなかから後継
者を一人決めることになる。そして、その後継者に会社の経営権が
承継されるよう、遺言によって自社株式や事業用資産を集中して遺
贈することになる。
しかし、後継者以外の法定相続人にも相続する権利があるため、
相応の対応を配慮しなくてはならない。
先代のオーナー経営者の遺産は、高額な評価価額となる自社株式
や事業用資産であることが多いため、その対応を誤ると、会社の経
営権をめぐって親族内の「お家騒動」に発展することがある。
親族内で事業承継した後継者の約8%は相続に際して何らかのト
ラブルを経験している、という調査結果もある。
相続紛争になる要因として、次のことが考えられる。
1.遺留分
被相続人であるオーナー経営者は、生前贈与、死因贈与あるいは
遺贈により自由に個人資産を後継者に取得させることができる。
しかし、配偶者や子供の生活の保障や、相続人の間の公平という
観点から遺留分の制度があり、オーナー経営者の個人資産の配分に
一定の限界が設けられている。
このため、自社株式や事業用資産を後継者に集中させようとする
と、他の法定相続人の遺留分を侵害することになる。他の相続人は
遺留分減殺請求権を行使することで、後継者への自社株式の集中を
阻止することができる。
2.特別受益
特別受益は相続人への生前贈与のことで、遺留分を算定する際の
基礎財産には生前贈与されたすべての資産が合算される。
このときの評価額は相続開始時点での評価になるので、例えば、
自社株式の生前贈与を受けた後継者が経営に尽力して株式の評価価
値を上げても、後継者への相続割合は変わらないまま、遺留分算定
の基礎財産額の全体が増加するという結果になる。
3.遺言
遺贈とは遺言により遺言者の財産を無償で譲渡することで、遺言
者の単独行為である。死因贈与は贈与者が死亡したことを条件とす
る贈与で、当事者間の事前の契約である。
遺言は遺言者の最終意思の尊重の観点から、一旦有効に作成され
ていても、遺言者の単独意思で自由に撤回し変更することができる。
したがって、たとえ公正証書遺言を作成していても、その後に遺
言者が単独で自筆証書遺言を作成して変更すれば、遺言を撤回する
ことができる。
死因贈与についても、原則として同様な取り扱いになる。自筆証
書遺言の効力に関する訴訟等が多い所以である。
近年、子息・子女が事業を承継することを拒んだため、オーナー
経営者の兄弟など子息・子女以外の親族が承継者となるケースもあ
る。
オーナー経営者が遺言で自社株式や事業用資産を後継者に集中さ
せる場合、後継者にならない法定相続人である子息・子女にも遺留
分減殺請求権があるため、トラブルの発生を防ぐよう事前に周到な
事業承継の準備をしておかなければならない。
鉄尾佳司