一般社団法人 東京都中小企業診断士協会 城南支部
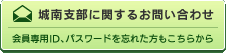
<前編のおさらい>
ジオラマ(立体模型)を全て手作りで制作しているD社は、マンパワー不足に陥っていました。その品質は伝統工芸品の域までに達していましたたが、制作に時間を要するため営業活動に時間がさけず、お客様に品質を理解してもらえないことも増えてきました。その結果、価格競争に巻き込まれ失注も増えてきました。
中小企業診断士(以下、診断士)として、D社の高い品質という強みを生かすため、都道府県から工芸品として表彰を受け、客観的評価を得て差別化をすること、それをHPやマスコミを使って広告宣伝を行い営業活動とすることを提案しましたが、D社のM社長からの反発は予想以上に強いものでした。
5.M社長への懸念への説明
・商工会議所や振興公社などは中小企業を助けるものです。最初は敷居が高く感じるかも知れませんが、診断士がそのために寄り添います。慣れるまでは同行もします。
・表彰制度はそれだけで広告宣伝になります。更に、定性的な評価に陥りがちと言われる工芸品に第三者の客観的評価を受けることは、自画自賛の営業とは異なりますので客観的な評価、差別化にもなります。口コミも広がりやすくなりお客様にも堂々と説明ができます。
・都道府県としている理由は国の表彰制度は競争が激しいためです。登記上の本支店は存在しなくとも、県内で実績があれば表彰対象となる地域もあります。国の表彰は大企業が目立ちます。経営革新計画の表彰はありますが、計画実行後に審査対象となり、今からでは数年かかります。
・補助金申請助成を行っている診断士は数多くいます。申請の目的は表彰制度と補助金受給と異なりますが、その内容は大きく変わりません。決して診断士に不可能とは思いません。
・とにかく、まずできることから始めましょう。今のままではM社長も言われている通りじり貧です。表彰制度応募の良いところは外注費や設備投資の必要が無いことです。
6.提案後のアクション
まずは、費用があまりかけないところから始めようとM社長の了承をえました。新米診断士ですが、私が、そのままお手伝いすることとなりました。目標は、D社所在地の某県の小規模事業者限定の表彰制度への応募と定め、活動を開始しました。
M社長は体調を崩していた時期に奥様の扶養家族となっていました。そのため、D社決算は、やや不明瞭なところがあり、追加支払いが発生しないか心配していました。
経営計画を立てるために、まずは過去の決算書の見直しを行いました。幸い脱税(脱税をしていると公共機関からの表彰対象から外れます)や修正申告の必要がありませんでした。時には激論となりながらも輝く将来像を共有し、申請の準備を行いました。
7.診断士としての所感
「賞金の出ない表彰制度に診断士が関わるのは珍しい」と県関係者の方から言われました。確かに報酬という面では難しいかも知れません。しかしながら、より直接的なお手伝いの方法の一つとして広告宣伝となります。
表彰制度を活用した支援を広めていきたいと思います。
福田 幸俊