一般社団法人 東京都中小企業診断士協会 城南支部
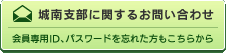
前回投稿では、「インドビジネス熱視線 ~期待とリアル(前編)」として「環境面」をテーマに、最近のインドの街の様子などについてお届けしました(https://www.rmcjohnan.org/report/kokusai_202502/)。後編では「ビジネス面」をテーマに、ビジネス進出先として選択する上での判断材料の一端をご提供すべく、インドの産業振興策や集積産業の地域性、物流インフラ整備状況、そして取引相手の常識・感覚の違いなどについて、実体験を踏まえてお伝えしたいと思います。
海外進出を検討する際、どの国に進出するか、進出国の選択に迷うのではないでしょうか。決定にあたっては実際、多くの判断要素を考慮する必要があります。例えば、海外進出の目的、海外で勝負したい商品・サービスが何か、対象国に自分の商品・サービスがフィットするのか、どうやって売るか、どのような文化・商慣習があるのか、ビジネスに関する規制はあるかなど、考慮すべきことの枚挙にいとまがありません。
今回は、皆様がインドを海外進出候補のひとつとして検討される際に、参考になる判断材料を少しでもご提供できればと思います。
■国による産業振興政策=プロ・ビジネス
候補国がどのような政策を推進しているか、その波に自身が乗れるかどうかは注目ポイントです。
インドはダイナミックな国です。GDP成長率に示される経済成長の勢いもさることながら、2014年以降10年以上かけて、モディ首相の牽引で数多くの政策イニシアティブが進められてきています。例えば以下の政策があります。
①メイク・イン・インディア
メイク・イン・インディアは文字通り、インド国内の製造業を強化しようという取り組みです。ゴールとして、2022年までに製造業のGDP占率を25%にすることや、1億人の新規雇用創出などが掲げられていました。規制改革を伴い、これまで電子機器、自動車、再生可能エネルギーなどで、多くの投資を呼び込みました。
②デジタルインディア
ブロードバンド網の整備や行政手続の電子化を通じてデジタル化を一気に進めようという取り組みです。代表的な政策として、アーダール(国民識別番号制度)の導入があります。いわゆるデジタルマイナンバー制度で、個人情報を集約管理するシステムです。これが整備され、銀行口座と紐づけられたことにより、補助金が中抜きされずに直接支援対象に届くようになるなど、行政の効率化が一気に進みました。
③ギフトシティー(Gujarat International Finance Tec-City “GIFT City”)
「ギフトシティー」はモディ首相の出身地であるグジャラート州アーメダバードにある経済特区の名称です。国内産業を新興するには豊富な金融資本も必要となります。そこで、外国資本を呼び込むため、一定の要件のもとで国内投資への免税特権を享受できるシステムを作りました。政権の後押しもあり、急速に開発・整備が進んでいます。
 ギフトシティーの様子
ギフトシティーの様子
(筆者撮影)
■集積産業の地域性
事業を効率的に展開するには、候補国の地域性と自身の事業との親和性も注目してみる必要があるでしょう。
インドは地域によって、集積している産業に特徴があります。例えば自動車であれば、首都デリーのあるデリー準州(北部)やベンガルールのあるカルナタカ州、チェンナイのあるタミルナド州(南部)などに多くの自動車・部品メーカーが集積しています。
またベンガルールはIT産業の集積地としても有名で、GAFAMなどが拠点を置き、インドのシリコンバレーとも称されています。
一方、西部のマハラシュトラ州の商都ムンバイは商業・金融都市とされ、多くの金融機関が拠点を置いていますし、ボリウッドとして有名な映画産業もあります。
■インフラ整備は開発途上
事業でヒト・モノを動かす過程で、候補国内の物流環境は重要な判断要素と考えます。
「World Economic Forum Global Competitiveness Report 2008-2009」によれば、当時インドのインフラスコアは「7段階中3.4」、「134か国中72位」と大きなボトルネックとなっていました。
その後、道路・空港の整備が進み、2019年版の同レポートでは、輸送インフラ領域において141か国中28位と上位になりました。依然、交通渋滞がひどく、物流面での非効率が指摘されていますが、国道網は2004年からの20年間で約2倍に広がって、空港数は2014年からの10年で2倍になりました。今後の混雑緩和に期待です。
■“カルチャー・ギャップ”(常識・感覚の違い)の存在
インドでは現地の方いわく、“カントリー・オブ・カントリーズ”と称されています。食事、言語、宗教など、地域性があります。したがってビジネス慣行も地域性を考慮した対応となることもしばしばです。とりわけビジネス取引の場面において、予め認識していると有用だと私が感じた実体験をシェアしたいと思います。
販路を見つける、店舗を出す、生産委託工場を見つける、というような局面では相手方と条件交渉が必要になるでしょう。一般化することはできませんが、インドのネイティブの方との交渉にあたって、私が体験した“カルチャー・ギャップ”には以下のような点があります。
・メールへの返信がなかなか来ない!
メールでの問い合わせに対する回答に期待するスピード感が異なっていると感じるかもしれません。とりわけ、難儀な照会・お願いに対しては返信が滞ってしまうケースがあるかもしれません。
対応策としては、直接コンタクトを行い、フェイスツーフェイスで確認することが望ましいのですが、それが難しいときでも少なくとも電話・オンラインミーティングを設定し、口頭での指差し確認をすることが近道です。
・Yes か Noかハッキリしない!
これは国民性ともいわれていますが、明確に”No”とは言わない傾向があります。したがって、現地で経験がないような生産設備やサービスを初めて導入するとき、Yesという回答に基づいて突き進むと予想外にとん挫するリスクとなりえます。依頼に対して”Yes(できます)”と色よい明確な回答が出てきたとしても、それが裏付けのある回答なのか、検証が必要です。
・時間を守らない!
会議の集合時間を守る、納期を守る、というのは当然の前提としてしまいがちですが、決してどの国・地域でも当たり前ではないということを再認識する必要がありそうです。特に納期は死活問題にもなりえます。細目な進捗確認と裏付け事実の回収をセットにすることで時間が守られることへの確度を上げることが必要です。
・期待通りの結果にならないことを想定しておく!
時間だけでなく、アウトプットの「エラーゼロ」を目指すマインドも当たり前ではありません。「できる前提で話を進めていたが、結果できなかった、もしくは不完全だった」、そのようなケースに直面しても驚かず、予め準備したリスクシナリオ下のプランBを実行に移すことが重要です。
・議論好き& 話が纏まらない!
これは有名な話かもしれませんが、話し出すと話が止まりません。しかも多数の方とのミーティングの場で、各々が議論を展開し、話が脱線・拡散していくことも普通にあります。
活発な議論はアイディアの宝庫ともいえますが、ファシリテーションスキルを発揮して、本題と別論点とを切り分けて、本題に意識を集中するように持っていくことが効果的です。
・数字を区切る単位が違う!(ラーク、クロール)
売上・コスト・ターゲット市場規模など、数字にまつわる話題も多いと思われます。日本のビジネスシーンにおいては、百万(million)、千(thousand)の単位で区切った数字を使用することが多いですが、インドでは10万(Lakh=ラーク)、1千万(Crore[Cr]=クロール)という単位で数字を区切ることもよくあります。契約には数字がつきものですから、お互いの頭に描いた値が一致していなかったというトラブルを避けるため、入念に数値の確認をすることをお勧めします。ちなみにラーククロール(10万×1000万=1兆)と2つを組み合わせて使われることもあります。慣れるまでは正直混乱します。
海外展開、特に新興国でのビジネスには“予想外”が色々あると思います。事前の情報収集で不安を軽減し、一歩ずつ前に進んでいく辛抱強さも必要かもしれません。
これまでインドビジネスについて、環境面(前編)、ビジネス面(後編)をお伝えしました。これらのコラムが、皆様のインドビジネスを検討する一助となれば幸いです。
【執筆者紹介】

榎本 雅也(えのもと まさや)
国内大手資産運用会社において、事業企画・投資商品の商品開発業務に約24年間従事。海外提携先との共同事業の推進やパートナーシップの管理などの業務に数多くかかわる。2021年中小企業診断士登録。
| コメントを投稿するにはログインしてください。 |