一般社団法人 東京都中小企業診断士協会 城南支部
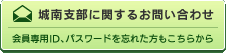
◆メディアは海外と比較するのが大好き
バブル期の「Japan as No.1」は遠い昔の話となり、メディアでは日本企業と欧米企業を比較して「日本は海外と比べてここが…」という論調の記事報道を目にすることが多くなりました。
日本企業が「進んでいる」、「遅れている」というのは、何を基準とするかによっても、問題を把握する切り口によっても異なりますが、ここではよく俎上に載る2つのポイントとして、「ジョブ型雇用」と「速い意思決定」について、私が当事者として実際に見聞きしたことをお話ししたいと思います。
◆ジョブ型雇用
「欧米の企業はジョブ型雇用がメインで、日本企業もその方向に進むべきだ」などとよく言われます。ジョブ型雇用を全面的に取り入れるのか部分的に良いとこ取りをするのか、など、やり方はいろいろあると思いますが、欧米の企業でジョブ型雇用が成立する、そもそもの背景を理解しなければ、どのように取り入れればよいか、判断がつかないでしょう。
確かに欧米の多国籍企業での働き方はジョブ型です。経験の浅い若手時代には専門領域が変わることもままありますが、中堅以上で専門領域を変更する人は少数派です。雇う側も雇われる側も専門領域を非常に大事にしていますので、“転社”はあっても“転職”は稀です。
例えば、ある企業でマーケティング部に欠員が出て採用活動をする場合は、マーケティングで“即戦力“となるのが絶対条件であることや、社内での昇進も、勤続年数や年齢性別など一切関係なく専門領域における能力の競い合いになります。
この“専門領域”で”即戦力”が成立する背景にはいくつかの特徴があります。
まず、雇われる側は同業の中をぐるぐる回遊する、ということです。「同業他社に移るなんて」という罪悪感など全くありません。雇う側も同業他社からの採用が当たり前です。会社を移って働く機会も、会社を移りながら専門性を高める機会も豊富です(シニアレベルだと雇用時に「退職後は一定期間同業他社で働かないこと」という契約を締結する場合があり、移れないことはありますが…)。
また、競争力のコアとなる部分以外(非競争領域)が標準化されていることも重要です。新しい商品のアイディアや新技術といった差別化に決定的に重要な部分は別として、社内システム(ITに限らず規程や組織構造などの仕組みも含む広い意味で)はどの組織も大体似通っており、他社からきても比較的早期になじめます。日本企業でよく聞く「ウチの会社は特殊だから…」とは異なり、汎用性を持たせて金銭的・時間的コストを縮減することに重きを置いているわけです。
さらに、レポーティングラインを構成する社員が皆同じ専門性を持っており、人事権もそのレポーティングラインに属していることも重要です。要するに、専門性を持った社員の上司は(通常は)もっと専門性が高く、その上司には評価権のみならず一切の人事権(昇給・昇格・採用・解雇)が属しているということです。部門長はジョブ型雇用で働く直属の部下を自分の高い専門性と経験に従って評価し、処遇や要不要を決める仕組みになっています。人事部門は社員の能力を評価することができませんので部外者であり、ほとんど関与してきません。
◆速い意思決定
欧米の多国籍企業は、企業規模を問わず意思決定が速いとよく言われます。拙速と言えなくもないとは思いますが実際に速いことは事実です。その背景は次に述べるようなことではないかと思います。
まず、欧米の多国籍企業は、権限(「DOA:自律分散型組織」と呼ばれます)がはっきりしています。職位に応じて何ができるのかが明文化されていますので、自分の権限内であれば契約の締結や資材の購入、社員の採用などは、誰に諮ることなく実行できます。職権を執行するのが楽しくてならない人達も多いです。もちろん失敗した場合の責任は取らされますが、万が一解雇されたとしても他社で仕事を探せばよいのです。
また、筆者が欧米の多国籍企業で勤務していた時には、欧米の多国籍企業には、変えたがりの文化もあるように思いました。終身雇用ではないですし、同期も、先輩後輩もありませんので、今までの仕組みや、やり方を変更するのに全く躊躇しません。日本企業では、「お世話になったあの人が作った仕組みだから…」といった遠慮や忖度をするケースも見かけますが、欧米企業では、特に外部から移って来た管理職は前任者とは一味違うことを誇示しなければならないため、とにかく変えたがります。時には、必要がなくても変えることもあります。セールスチャネルの変更や、新規業者の採用や、ITの変更など、変えることの意思決定は積極的に行います。
さらに、欧米の多国籍企業では、シニアレベルになればなるほど、「自分が独走してもまわりがどうにかフォローする」と思っている管理職が多いこともあります。日本企業であれば、「現場に迷惑がかかるから」といった発想で、根回しや調整に時間をかけるようなケースを見かけますが、欧米企業では、そんなことはお構いなしに、意思決定を行います。日本企業で意思決定のスピードをあげようとする場合、こちらもジョブ型雇用同様、そもそもの背景を理解しなければ、どのようにスピードをあげればよいか、判断がつかないでしょう。
◆結局どうなのか
今回は一例として、よく俎上に載る「ジョブ型雇用」と「速い意思決定」について見てきました。結局は、会社の仕組みや制度は積み重ねてきた文化や歴史といった文脈の上にあって成り立ち機能するもので、一律に「進んでいる」、「遅れている」という尺度で測れるものではないということではないでしょうか。
自社が、過去から積み上げてきた文化や歴史、現在置かれている状況、組織としてのありたい姿を実現するために、どのような仕組みや制度がよいのかは、会社によって異なります。本コラムが、皆様の最適解を見つける一助となれば幸いです。
【筆者紹介】
河野 和彦(かわの かずひこ)
新卒で日本石油(現在のエネオス)に就職。早々にドロップアウトし米国留学を経て数社の外資系企業に勤務。医師向けの医薬品・医療機器製造販売業における経験がメインで、専門は新卒から一貫してファイナンス。2022年にサラリーマンを引退し、同年5月中小企業診断士登録。
| コメントを投稿するにはログインしてください。 |