一般社団法人 東京都中小企業診断士協会 城南支部
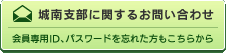
はじめに
城南支部には三種の神器と呼ばれる取組があり、その一つに「チューター制度」があります。本制度は、他支部が城南支部を参考に導入を始めるなど定評のある制度です。
今回は、その「チューター制度」の事務局長として運営に携わっておられる磯島さんにインタビューをさせていただき、若手診断士のキャリア形成を後押しする青年部の活動についてお伺いました。
磯島さんの中小企業診断士としての経歴
(内藤)まずは、磯島さんの中小企業診断士としての経歴をお聞かせください。
(磯島)定年後のキャリアを見据え、50歳を過ぎてから中小企業診断士資格を取得しました。6年目を迎えた現在も企業内診断士として活動しています。診断士としての目標は、定年後の経済面の支えとするだけにとどまらず、社会とのつながりを持ち、誰かの頼りにされるような存在であり続け、自己実現を図ることです。これまでの活動内容としては、コロナ禍における補助金申請支援や創業支援などの公的な支援に加えて、本業のテレビ局での情報番組制作の経験を活かし、民民契約での中小企業の広報業務支援にも取り組んでいます。
青年部の役割とチューター制度の位置づけ
(内藤)城南支部の青年部が担っている役割について教えてください。
(磯島)近年、多くの新入会員を迎え入れている城南支部ですが、かつては、各支部が1人でも多くの新入会員獲得を目指し活動していました。城南支部も様々な施策を行っていましたが、単に会員数を増やすという取り組みだけではなく、支部入会後の質の向上も求められるようになってきました。
また、診断士資格取得の入り口は共通でも、その先の診断士として目指すキャリアは十人十色で、これといった正解がある訳ではないと考えています。そうした中、青年部では、何から始めれば良いか分からないという新入会員から5年目までの若手会員を対象に、診断士としての「競争戦略」と「成長戦略」を策定できるよう、また診断士同士のネットワーク構築や支部活動を理解できるようサポートする役割を担っています。
(内藤)そのような役割を担っている青年部において、チューター制度とはどのような位置付けなのでしょうか?
(磯島)チューター制度は青年部活動の一環として、入会直後の会員が孤立することなく、診断士活動に参加できる環境を提供しています。元々、チューター制度は会員部の管轄でしたが、若手会員を対象とした活動ということで、任意団体であった「新談士の会」と共に、2023年度から青年部が管轄することになりました。これにより、若手会員向けの活動を青年部の傘下で一元管理することになり、会員の皆様に質の高い、一貫したサービスをお届けできる体制となりました。チューター制度は2年ごとに事務局長が交代するルールとなっており、今年度は3代目の私が2年目の時期となり、チューター制度の開始から6年目を迎えています。また、チューター制度の事務局長に併せて「新談士の会」のコーディネーターも務めています。
「チューター制度」と「新談士の会」の今年度の取り組み
(内藤)「チューター制度」と「新談士の会」を通じて青年部がになっている役割についてお伺いしましたが、青年部管轄となった2つの活動の今年度の取り組みについて教えてください。
(磯島)開始から6年目を迎えた「チューター制度」と「新談士の会」において、事務局長・コーディネーターとして今年度特に力を入れたのは、
1. チューターとチューター事務局の負担軽減
- 各チューターグループの交通費・会議費の公費負担化
- 研究会見学会の自由参加制度導入(従来の引率制度の撤廃)
2. 新入会員の満足度向上
- 交流イベントの企画・運営
- グループ外交流の促進(グループコンテンツの共有や所属グループの垣根を超えたオープンミーティングの試験運用)
3. スキルアップ機会の創出
- 「新談士の会」を通じたセミナー開催
- 城南支部の主要プログラム(城南コンサル塾・城南プログラム・チューター制度)への橋渡し
新入会員の満足度向上に関しては、まだ効果を計測できていませんし、道半ばではありますが、オープンミーティングや新入会員の手による新談士の会の自主運営化などの流れを受けて、満足度が向上していることを期待しています。
チューター制度の今後の課題
(村上)チューター事務局長として、上手くいったことをお伺いしましたが、逆にもっとこうすれば良かったと感じられていることはありますか?
(磯島)事務局で今まさに1年目の振り返りを行っているのですが、リアルにコミュニケーションを取れる機会をもっと提供できればと良かったと思っています。リアルで集まりたいという会員の皆様の声はあるのですが、チューター制度が大規模になるにつれ、日程や場所の調整が大変になってきているのも事実です。より密なコミュニケーションを行うためにも、来年度に向けて改善していきたいと考えています。また、チューターの方々のモチベーションやスキルが均一化されていないことも課題として捉えていますが、前述の通り診断士の姿に正解はないので、色々な方がいて、色々な形があって良いとも思っています。
来年度に向けた抱負
(村上)最後に、来年度に向けた抱負を伺えればと思います。
(磯島)城南支部はおかげさまで多くの新入会員の皆様が入会されています。一方で、会員数が増え過ぎたことによる弊害も生じていると感じています。城南支部には、プロコン養成を目的とした城南コンサル塾がありますが、現在は応募倍率が高く、受け入れ枠を倍にしても希望者全員を受け入れることが出来ず、狭き門となっています。
この城南コンサル塾、城南プログラム、チューター制度を総称して、城南三種の神器と言われていますが、この城南三種の神器がシームレスで一気通過に繋がることが、これからのあるべき姿だと考えています。
少し話は変わりますが、私が入会した際に、当時の宇野支部長をインタビューする機会があり、そこで感銘を受けた言葉がありました。「城南支部に限らず、診断士は多種多様な業界経験を持つ人々が「診断士」という共通言語を持って集まっています。その知見を上手く集約できれば、グローバルコンサルティングファームにも負けないサービスを提供できる可能性があるのに、現実はそうはなっていません。その理由を考えると、各自が様々なバックボーンで色々な知見を持っている一方で、スキルの均一性が担保されていないことに加え、可視化が十分ではない、ということが挙げられると思います。また、診断士として補うべきスキルが十分に共有されていないことも問題だと考えています。そのため、診断士としてのあるべき姿を目指すために、城南プログラムとチューター制度を設立しました。」というものです。
チューター事務局長の2年任期の中の残り1年で、チューター制度が真の意味で城南コンサル塾、城南プログラムへの橋渡しとなる役目を担える形になることを目指していきたいと考えています。来年度に向けた具体的な改善策としては、
– グループを超えた交流の拡充(オープンミーティングの安定した運用)
– 「新談士の会」の質の向上と標準化
を行っていき、より効果的な制度運営を目指していきたいと思います。
インタビュー風景
Zoomでオンラインインタビューさせていただきました。

【執筆者】

内藤 裕太郎(ないとう ゆうたろう)
2021年診断士登録。城南支部には2024年に入部し、新入会員としてチューター制度に参加。SIerでのシステム開発、スタートアップ・Webメディア・動画配信プラットフォームでのデータ・AIを活用したビジネス課題解決を経て、2025年2月末で退職し、診断士として独立。

村上 雅一(むらかみ まさかず)
企業内診断士。2024年診断士登録。同年、城南支部に入部し新入会員としてチューター制度に参加。本業は、ネットワークインフラ構築企業の代表取締役。
| コメントを投稿するにはログインしてください。 |